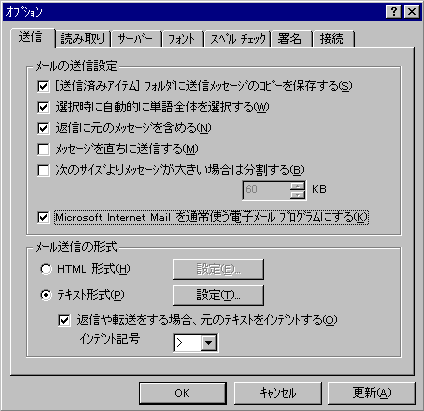
オプションダイアログの設定
この「オプション」ダイアログには何枚かの「タブ」と呼ばれるものがあります。左から「送信」「読み取り」「サーバ」「フォント」「スペルチェック」「署名」「接続」と7枚のタブがあり、それぞれに「タグ」のようなものがありますから、これをクリックするとその「タブ」が表示されます(前面に出てくる)。
「送信」タブから順に説明していきましょう。
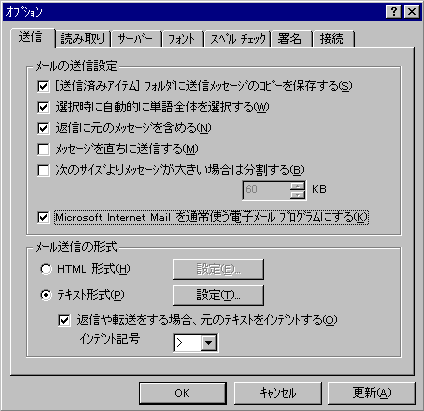
この「タブ」にはたくさんの「チェックボックス」があります。「チェックボックス」とはクリックをしてチェックすることで、そこに書いてあるものを採用するかしないかを選択するものです。
またこのタブには「ラジオボタン」というものもあります。これは複数の選択肢の中から一つを選択する場合に用います。
では実際の内容を追って見てみましょう。
「メールの送信設定」という枠の中に、6つのチェックボックスと一つの数値ボックスがあります。
1.「[送信済みアイテム]フォルダに送信メッセージのコピーを保存する(S)」
これは言葉の通り送信したメールを「送信済みアイテム」というフォルダにそのコピーを保存していおくかどうかを決めるものです。これはチェックしておいた方がいいと思います。こうしておけば自分がいつだれにどんなメールを出したのかが、後で確認することができます。
2.「選択時に自動的に単語全体を選択する(W)」
これは重要でないので説明を省きます。チェックしてもしなくてもいいです。
3.「返信に元のメッセージを含める(N)」
多くのメールソフトにはメールを受けとった相手に「返事」を出す時に便利で簡易な「返信メール」という機能があります。
通常メールを出す場合、宛て先(相手のメールアドレス)とタイトルは入力必須です。タイトルはいいにしても、宛て先の入力は大変面倒です。なにしろインターネットメールの宛て先は長いですからね。しかし大抵のメールソフトはアドレス帳を備えていて、そこに登録しておけば、いちいちキーボードから入力しないで済むようには工夫されています。それでもアドレス帳から選択をしなければなりません。
「返信メール」機能は、ある人から来たメールを読んでいる時にメニューなりボタンから「差出人へ」というのを選ぶと、宛て先にはその相手のメールアドレスが、タイトルには、その人のからのメールのタイトルに「RE:」というものを冠したタイトルを自動的に付けてくれて、後は本文を書くだけでいいようにしてくれます。大変便利な機能で文通的なやり取りには欠かせないものです。
その時に更に相手の文章を引用するということをよく行います。手紙には電話と違って大きなタイムラグがありますから、出した本人もどのような内容を出したかは覚えていません。またいくつかの話題が含まれるのが普通ですから、返事を出す側が相手からの質問や話題に対して書いても、何をいっているのか分からない場面が多々あります。
そこで相手の文章をちょこちょこと引用することで話しの流れを作り出す訳です。丁度電話で話しているような効果を醸し出すことができます。 これが電子メールのもつ、普通の手紙にはない一つの流儀であると理解して下さい。
まあ、上記のようないわれからして、ここはチェックをしておくのが普通です。チェックをすると全文が引用されますが、冗長な部分は後で削除すればいいので、不都合はないと思います。
また引用時に、その部分が引用であることを明確にするため、先頭に「>」などの記号を付けるのが普通です。この設定は後述します。
4.「メッセージを直ちに送信する(M)」
これはメールを作成し、「送信」っとやった場合に、即座にサーバに送るか一旦「送信アイテム」フォルダに保存するかを指定します。
通常会社での環境のように常時接続の場合は問題ないのですが、ダイアルアップ環境の場合は、サーバに接続している間は、プロバイダの接続料と電話代の双方が課金されます。しかしたとえばメール送信の場合、作業的に一番時間がかかるのはメールの文章をかくことですが、この時にサーバに接続している必要はない訳です。また受けたメールを読む場合も、別に接続している必要はありません。一旦自分のパソコン内に取り込んでしまえば、接続を切って、後でゆっくり読めばいい訳です。
ですから最近のメールソフトは必ず「オフライン」(接続されていない状態)で作業ができるようなっています。
昔はダイアルアップ接続なるものはインターネットの世界にはなかったので「オフライン」という概念はなく、接続してないと、ソフトを起動することすらできませんでした。この接続した状態を「オンライン」と呼びます。
ほとんどの作業はこの「オフライン」で行います。メールを読んだり書いたりといった作業です。作成したメールは一旦「送信アイテム」フォルダに保存するようにしておきます。そしてこれらのメールをサーバに送ったり、サーバに到着している自分へのメールを受け取るのは、当然サーバに接続する必要があります。ある意味必要なのはその瞬間だけです。時間的にも数秒です。これを行うのがメイン画面の「送受信」ボタンです。
という訳でこのチェックボックスをチェックするのは、通常は常時接続環境の人だけです。常時接続の場合、なにも一旦フォルダに溜めておく必要はないので、その都度サーバに送っても構わない訳です。ダイアルアップの場合は、チェックをしないで下さい。
ただしその場合は、「送信」をしただけでは実際にはメールが送られず、「送信アイテム」フォルダに溜まっているだけですから、必ず「送受信」を最後に行って、メールをサーバに送って下さい。たぶん「送信アイテム」フォルダに送信メールを溜めたままでソフトを終わらせようとすると警告されるはずです。
5.「次ぎのサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B)」
これも説明を省きます。ただしチェックは「しない」で下さい。
6.「Microsoft Internet Mailを通常使う電子メールプログラムにする(K)」
これはチェックしておいて下さい。これによってホームページなどでメールを出すような操作を行った場合自動的にこのInternet Mailが起動されます。
7.「メール送信の形式」
この枠の中にあるのが「ラジオボタン」です。チェックボックスと違って丸いマークです。このラジオボタンは、「HTML形式」と「テキスト形式」の2つが排他(どちらかだけ)選択になります。ここでは必ず「テキスト形式」を選んで下さい。「HTML形式」では受け取る人によっては読むことができません。因みにHTMLとはHyper Text Markup Language の頭文字です。
となりの「設定(T)...」ボタンを押すと次の「テキスト形式の設定」ダイアログが表示されます。説明は省きますが、図のように設定してください。(多分このような設定になっているとは思いますが)
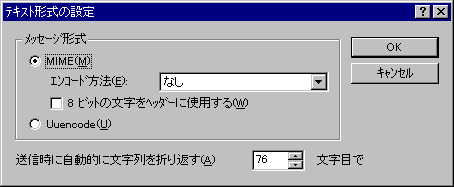
8.「返信や転送をする場合、元のテキストをインデントする(O)」
これが先ほどの、相手文章の引用時の引用記号の指定です。「インデント」というのは「段落を下げる」ことなのですが、要するに相手文章の引用は段落を下げそこに記号を入れるということです。
記号は「>」「|」「:」の3種類が選べるようですが、「>」が一般的 ですから、これにして下さい。
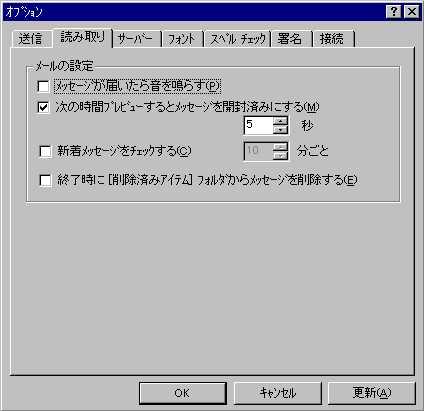
1.「メールが届いたら音をならす(P)」
これは常時接続している人が、定期的にサーバに新着メールを確認しにいくので、その時にメールが届いていたら音をならして知らせるという意味です。ダイアルアップの人には基本的に関係ありません。
2.「次の時間プレビューするとメッセージを開封済みにする(M)」
まず「プレビュー」ですが、これは受信メールを正式に見る前に軽くさわりを見るといったニュアンスです。受信メールを正式にみるには、そのメールのタイトルをダブルクリックします。そうすると別のウィンドウが現れてそこにメールが表示されます。これを行うことで「メール」を読んだことになり、そのメールは「開封済み」となります。「開封済み」になると目次の当該メールの前のアイコンが変わり、そのメールが開封済みかそうでないかが分かります。このようにするのではなく、あるメールをクリックするだけで、下の方にその内容が表示されます。これは実はプレビューなのです。全文をちゃんと読むことができるので、どうしてこれをプレビューと呼んでいるのかは分からないのですが、これは正式に見たことにはならないようです。
しかし今も述べた様にプレビューでもちゃんと読むことができるので、あるメールに対してプレビューを何秒か続けたら、そのメールは正式に読んだことにするか、つまり「開封済み」する時間を設定するのです。これは好き好きですが、私はこのプレビューで十分全文読めるので、いつもこれだけで読んでいます。ですから5秒ほどプレビューしたら開封済みになるように設定しています。
3.「新着メッセージをチェックする(C)」
これは常時接続の場合に何分おきにサーバに新着メールが来ているかをチェックするかの設定ですから、ダイアルアップ接続の場合はチェックする必要はありません。
4.「終了時に[削除済みアイテム]フォルダからメッセージを削除する(E)」
メールを削除した場合は、すぐには削除されず、一旦[削除済みアイテム]フォルダに格納されます。削除に関してはワンクッションおく訳です。デスクトップにある「ごみ箱」と同じような趣旨で、誤操作による大切なメールの削除を防止します。
しばらく使い方に馴れるまでは、不用意にメールを消してしまわないようにここのチェックはしないでおきましょう。
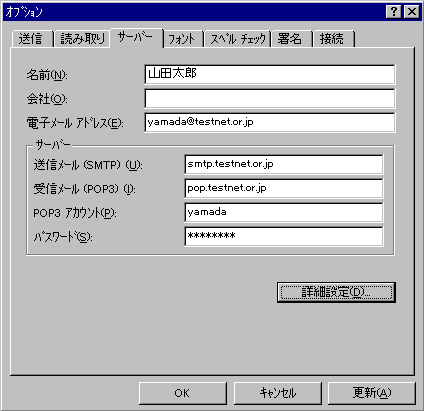
基本的に設定ウィザードで設定済みのはずですが、非常に重要なところですから確認しましょう。プロバイダなどから来た書類などをよく見て正確に記述します。ここを正確に記述しないとメールの送受信が一切できません。
1.「名前(N)」
ここは普通にあなたの名前を記述します。受け取った側の「差し出し人」欄に表示されるようになります。
2.「会社(O)」
ここは個人ならば、特に記述する必要はありません。
3.「電子メールアドレス(E)」
メールアカウント@サーバドメイン名という形式の自分のメールアドレスを正確に記述します。これを間違えると返信メールが帰ってこなくなります。
4.「送信メール(SMTP)(U)」
送信用のサーバ(SMTPサーバ)のサーバ名を記述します。
因みにSMTPとは、Simple Mail Trasnport Protocol の頭文字です。
5.「受信メール(POP3)(I)」
受信用のサーバ(POP3サーバ)のサーバ名を記述します。
メールサーバには上記のように送信用と受信用のサーバがあります。ただし多くのプロバイダでは双方に同じサーバを使っており、メールサーバとしか書類に書いてない場合もあるでしょう。その場合はそのサーバ名を双方に記述すればいいだけです。
因みにPOPとは、Post Office Protocol の頭文字です。
またPOP3サーバはPOPサーバと書いてある場合もあるので、気をつけましょう。
6.「POP3アカウント(P)」
通常は「メールアカウント」と同じ意味です。書類などには「メールアカウント」と書かれている場合もあるでしょう。「メールアカウント」とは普通はメールアドレスの「前半部分(@の前)」ですが、たまに違う場合もあるので気を付けましょう。また多くの場合、プロバイダの「ユーザID」とも同じはすなので、特に「アカウント」というものが記述されていない場合は「ユーザID」を指定してください。
プロバイダによって呼び名などがまちまちなので、上記の説明からでも「POP3アカウント」に何を設定すべきかわからない場合は、プロバイダに問い合わせて確認してください。
7.「パスワード(S)」
これも通常はプロバイダへの接続時のパスワードと同じものです。書類に「パスワード」というものが一つしかなかったら、それを記述します。もしプロバイダへのユーザIDとメールアカウントが別ものもであった場合、パスワードも別のものがあるかもしれないので、よく書類を確認しましょう。
これはデフォルトままで、触るのはやめましょう。わけのわからない文字になってしまったら大変ですから。
ここもとりあえず設定する必要はありません。
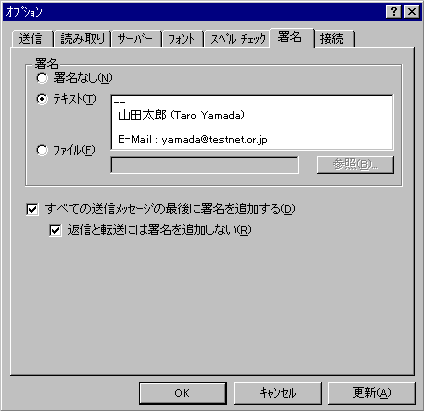
1.「署名」
「署名」なんてものを今更説明はいらないと思いますが、ここでメールにどのような署名を付けるかを設定します。
ラジオボタンで「署名なし(N)」を選択した場合は当然署名はなしです。
「テキスト(T)」を選択した場合は、その右のテキストエリアに書いたものが採用されます。「ファイル(F)」を選んだ場合は、署名をあらかじめあるファイルに書いておき、そのファイルをここで指定します。
まあ「テキスト(T)」の方を選んで、そこに書いておけばいいでしょう。
署名の形式ですが、名前とE-mailアドレス、ホームページがあればそのアドレスを書くくらいが一般的です。よく住所や電話番号まで書く人がいますが、あまり好ましくありません。昔通信環境があまり整っていなかった頃は、少しでも送信量を減らすために、署名は4行までという暗黙の決まりもあったくらいです。今はそれ程うるさいことを言う人もいませんが、あまり派手な署名は避けましょう。
2.「すべての送信メッセージの最後に署名を追加する(D)」
署名を設定しても、通常はそれだけではメールに書かれ(挿入され)ません。基本はメールのウィンドウの「挿入」メニューの「署名」で本文に手動で挿入します。しかしここをチェックしておけば、それをしないでも自動的に本文に署名が挿入されるようになります。
3.「返信と転送には署名を追加しない(R)」
私はこれをチェックしています。なぜなら返信の場合、元の文章を引用しますが、なぜかその引用の前に署名が付いてしまいます。署名はやはり最後につけたいので、いちいち最後に移動しなければなりません。そんなことをするくらいなら自動挿入は使わず、手動挿入にした方が楽です。ここをチェックすると返信と転送の場合には署名の自動挿入をしなくなります。
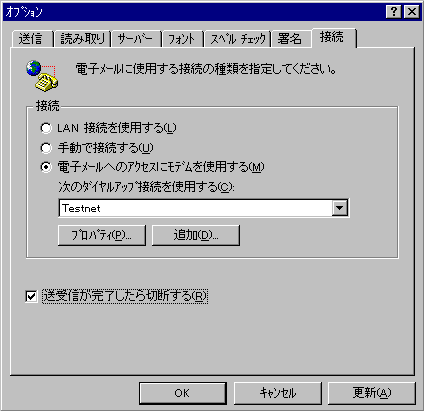
1.「接続」
ここも設定ウィザードで設定してあるはずです。「電子メールのアクセスにモデムを使用する(M)」を選択して、「次のダイアルアアプ接続を使用する(C)」コンボボックスでプロバイダへのダイアルアップ接続を指定します。
簡単な設定ですが、忘れると全く通信ができないので、気をつけましょう。
2.「送受信が完了したら切断する(R)」
ここをチェックしておくと、サーバへの送受信が完了したら、サーバへのダイアルアップ接続を、自動的に「切断」してくれます。通常はチェックしておきます。これは接続時に変更することもできます。
以上で設定は終わりです。それでは快適なインターネットライフをお過ごし下さいませ。